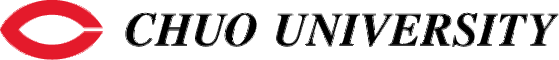澄み渡る空の下、合宿5日目が始まりました。
球場に到着すると、昨夏の甲子園に出場した岡山学芸館の高校生と合流し、アップを行いました。本日のアップでは、集団走の後に入念なストレッチを行い、さらに動的ストレッチへと移りました。心拍数を上げると同時に、パフォーマンスの向上を目的とし、全員が高い意識持って取り組みました。
その後、トレーニングへと移りました。本日のトレーニングは、ポール間6本、ポール間ハーフ6本を行いました。体が疲労している中で、どれだけ自分を追い込めるか、一人一人が高い志を持って取り組みました。また、最後の1歩まで全力で走り切れるか、持てる力を出し切れるかを選手全員で指摘し合い、実りあるトレーニングとなりました。
続いて、技術練習に移り、午前は守備練習、午後は紅白戦を行いました。
キャッチボールを行った後、シートノックへ移りました。強風の中でのノックとなりましたが、送球ミスや捕球ミスといった細かなミスが目立ちました。しかし、試合はどのような状況下であれ、行われます。状況を言い訳にして普段通りのプレーが出来ない事は、決して許されません。そして、捕球や送球の全てにおいて最後まで責任を持つよう、小泉監督から御指摘を頂きました。勝つ為には、最善の準備を怠らないことが不可欠です。その意識を改めて共有し、選手全員が一球一球に対して高い集中力と責任感を持ち、精度を追求して参ります。
昼食後は紅白戦を行いました。野手陣は、甘い球を一球で仕留める確実性、積極的な走塁と打球判断、中継プレーの精度を、投手陣は、低めに集める制球力とファーストストライクの精度をテーマに掲げ、紅白戦に挑みました。
紅白戦を通じて打者陣は、初球から力強いスイングを仕掛ける選手が多く見られました。積極的にバットを振ることで、タイミングをつかみやすくなり、その後の安打にもつながります。また、投手の視点から考えても、早いカウントで思い切りスイングされることでプレッシャーがかかり、制球が乱れる要因となります。この攻撃的な姿勢を継続し、関東大会でも生かしていきたいと考えています。また、走塁に関しても、浜松合宿において重点的に取り組んでいることもあり、以前より次の塁を狙う意識や、相手の隙を突く走塁が目立つようになりました。一方で、塁上での一瞬の判断には課題が残りましたが、チーム全体として走塁に対する意識が高まりつつあり、確実に成果が表れています。こうした攻めの走塁をさらに精度の高いものにし、試合の流れを自分たちのものにできるよう、一層の意識向上と実践を重ねていきます。関東大会に向けて、これまでの取り組みを自信に繋げ、より完成度の高いプレーを目指して参ります。
一方、投手陣は決め球の精度や最後まで投げ切る力といった課題が浮き彫りとなる結果となりました。投手有利の組み立てや、要所での制球力向上が求められる場面が多く見られました。投手一人ひとりには、それぞれ役割があります。その役割を十分に理解し、投手陣が一体となって試合に臨めるよう練習に取り組んで参ります。また、今後は、一球ごとの意図を明確にし、より実戦を意識した投球ができるよう精度を高めていく必要があります。関東大会に向けて、自らの課題と真摯に向き合い、どの相手に対しても自信を持って投げ込めるピッチングを追求して参ります。
そして、本日の紅白戦を通じて得られた成果は、自信へ繋げ、関東大会までに更に磨きかけて参ります。一方で、課題として浮き彫りとなった点については、一つひとつ真摯に向き合い、修正と向上を重ねながら克服していくことが求められます。関東大会本番で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、日々の練習をより実戦的なものとし、個々の成長とチーム力の向上に努めて参ります。
本日は、多くのOBの皆様や応援してくださる方々より、温かい差し入れを頂きました。中央大学準硬式野球部の諸先輩方が築き上げてくださった素晴らしい伝統とチームがあるからこそ、今こうして多くの皆様に支えられ、応援して頂いているのだと改めて実感致しました。先輩方の努力と想いに恥じぬよう、そして応援してくださる皆様への感謝の気持ちを忘れず、より一層の成長を遂げ、強い中央大学準硬式野球部を築き上げて参ります。
そして最後に、私自身、今シーズンが学生野球最後の年となります。昨年1年間主務を務めさせて頂き、大きな成長を遂げると同時に、多くの皆様のご支援のお陰で大好きな野球が出来ている事への感謝の想いを強く実感しました。家族、友人、そしてこれまで支えて下さった皆様への感謝を胸に、1年間全力で駆け抜けます。そして、仲間とともに最高の瞬間を作り上げられるよう、明日も全力で、想いを込めて白球を追いかけます。
坂井直行様
渡邉洋平様
谷川修一様(平成10年卒)
豊田和晃様(平成19年卒)
功刀史也様(令和7年卒)
城航希様(令和7年卒)
加藤真樹郎様(令和7年卒)
酒井尋如(新4年・岡山学芸館高)